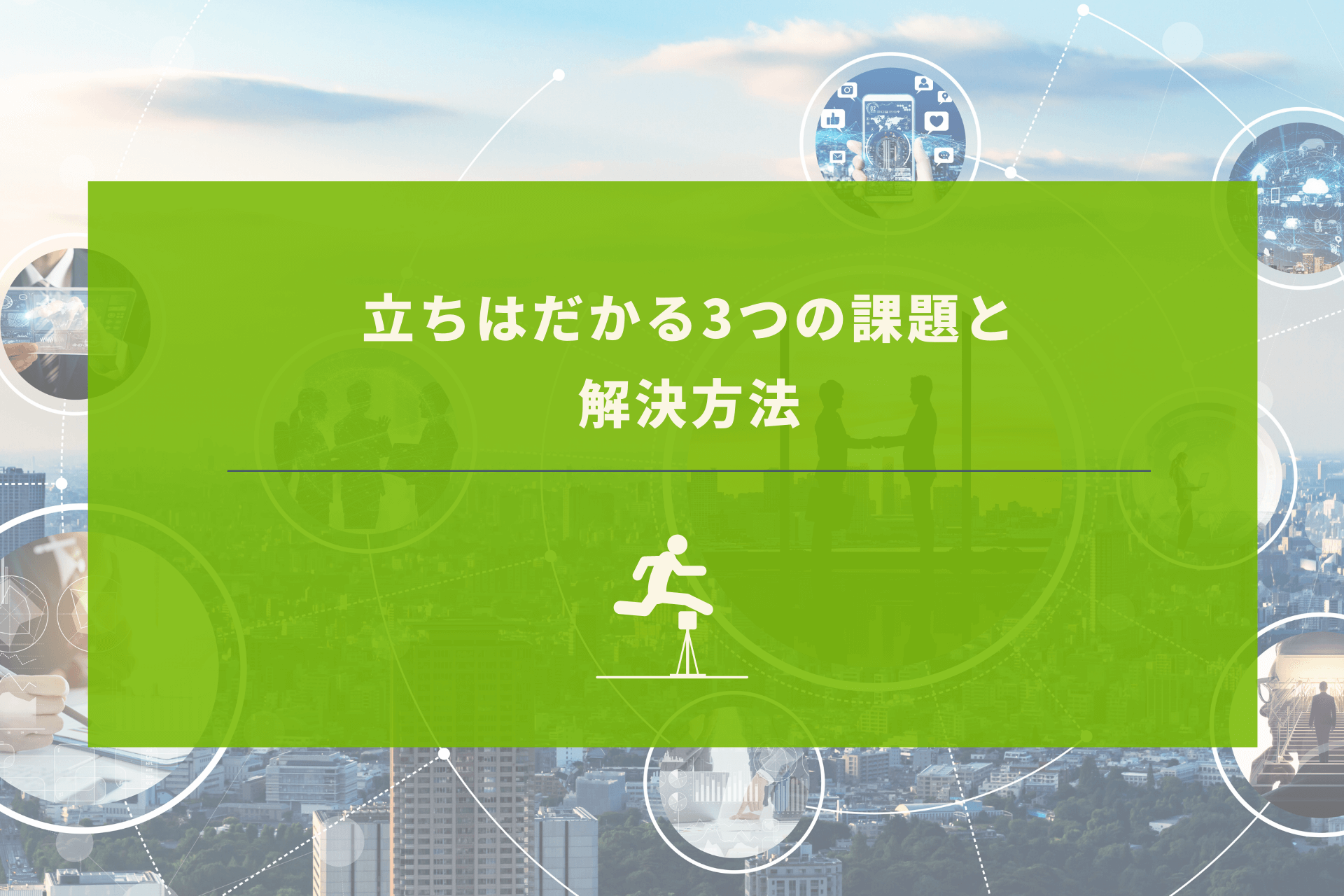
企業は人材育成を効率的に行い、個人の持つ能力を最大限に発揮し、仕事に取り組んでもらいたいと望んでいるはずです。
しかし、実際に育成を進めていく中で、さまざまな課題が持ち上がり途中で中断してしまったり、思うような効果が上がらず諦めてしまったりするケースが多々あります。
ここでは、人材育成に立ちはだかる3つの課題と解決方法についてご紹介します。
- 時間の課題
- 意識の課題
- 時代の課題
目次
人材育成とは?
企業における人材育成は、社員に必要なスキルや知識を身につけさせることで、企業の目標達成を可能にする重要な仕組みです。単に技術や専門知識の向上にとどまらず、ビジネスマインドの醸成や帰属意識の向上にまで範囲が広がります。
例として、DX人材の育成が挙げられます。テクノロジーの急速な進化に対応し、企業のデジタル変革を推進するためには、従業員が新しい技術を積極的に学び、活用できる能力が求められます。企業がDXに関する知識とスキルを持った人材を育てることで、イノベーションを促進し、市場での競争力を高めることが出来るようになります。
人材育成は、従業員が自らのキャリアを形成し、成長していく過程を支援するとともに、企業が持続可能な成長を遂げるための基盤を築く役割を担っています。このように、人材育成は個々の従業員の能力向上だけでなく、企業全体の目標達成に不可欠な投資と言えるでしょう。
人材育成を阻む時間の課題
ひとつ目の課題は『時間』です。
労働政策研究・研修機構の調査によると、人材育成における課題の第一位は『時間的余裕がない』になっています。
企業は人材育成をしたいと思っていても、時間がないため十分にできないと考えているのです。
どのようなことが原因で時間が課題となっているのでしょうか。
労働、雇用体系の多様化
以前の日本は終身雇用が当たり前で、正社員として働くのが大多数という時代でしたが、現在は短時間労働、パート、アルバイト、フリーランスというように、働き方や雇用形態が多様化してきています。
そのため、管理職が正社員で他の職員はパートという職場や部署も珍しくなくなってきています。
パートやアルバイトの場合は、働く時間が限られており、シフト制で勤務していることも多いため、教育をしたくてもまとまった時間を取るのが難しい状況になっているのが現状です。
人材不足による労働量の増加
どの業界も人材不足が叫ばれており、ひとりにかかる負担が多くなっています。
残業は当たり前、休日も会社には行かないけれど家で仕事という人も多いのではないでしょうか。
そのような状況の中で人を育てる時間的な余裕がなくなるのは、当たり前かもしれませんね。
人材育成の優先順位が低い
多忙な毎日で時間に追われるように過ごしていると、どうしても目の前の業務に意識が集中し、直接仕事に影響の出にくい部分は後回しになってしまいます。
企業はいかに社会貢献をしながら業績を伸ばすか、会社として成長させるかに焦点が当たります。人材を作ることがどのような効果を生むのかという、人材育成の目的をはっきりしていないと優先順位は下がっていきます。
時間ができたら・・・と思っているうちにあっという間に時間だけが過ぎ、次世代を担う人材がいないということになってしまいます。
人材育成の邪魔をする意識の課題
ふたつ目の課題は『意識』です。
計画や結果は目に見えてわかりやすく評価しやすいのですが、意識は形にしにくいため少々厄介です。
具体的にどのような意識が人材育成を邪魔するのでしょうか。
人材育成に対する認識が低い
それぞれの企業には独特の考え方があると思います。
企業風土と表現されることが多いですが、企業全体の価値観が人材育成について明確なものを持っていないと、研修等を実施したとしても表面的であいまいなものになってしまいます。
人材を育てることは、誰かひとりがするのではなく、組織や会社全体で取り組まなければ上手くいきません。
社員ひとりひとりの意識が良い教育環境を作るのです。
担当者の教育が伴っていない
人材育成というと、入社したての若手社員に対してというイメージになりがちですが、教育を担当する中堅社員の教育も重要になります。
管理職になったからといって全員が部下育成に長けているとは限らず、指導する側を育てるところから始めなければなりません。
現状把握が薄い
育成を進めるためには、目標設定が大切になります。
そのため、どのような人材をいつまでにどのくらい育て上げたいのか、どのようなスキルを習得してもらうのか、担当や役割分担をどうするかなど、事前準備が必要です。
人材育成をするには、現状の課題や不足な人材などの把握をし、教育方針を具体化します。
この現状把握が十分でない場合、どんなにがんばっても有効な結果には結びにくくなります。
ホスピタリティを軸としたリーダーシップで、スタッフを生かしチーム一丸となって業績を最大化するマネジメントを学びます。また、リーダー同士の想いも共有し、明日からのマネジメントの力となるような研修カリキュラムです。
人材育成のハードルを上げる時代という課題
3つ目の課題は『時代』です。
時代の流れに敏感になれるか、対応できるかがカギになります。
業界や世間の流れ、流行りなどにはアンテナを張り情報収集をしても、それ以外の部分に関しては手が回らないというのが現状かもしれませんね。
若者の仕事に対する認識の変化
社会人としての心得や仕事に対する考え方も、時代と共に変化してきています。
仕事優先で家庭やプライベートは二の次、休みも付き合いや接待で終わるという時代はもう古くなっています。
今は、仕事よりもプライベートを優先させたい人が増え、スキルアップや昇進などにあまり興味を持てない若者も増えてきています。
そのため、人材育成をしようとしても会社と若手職員との間に見えない厚い壁ができてしまうのです。
管理者が時代の変化を実感していない
ある一定以上の年齢では、『仕事は先輩の背中を見て覚えるもの』という認識があります。
これは間違ってはいませんが、現代には通用しにくいものとなっています。学校教育が変化しており、20年前、30年前の常識は今や非常識とさえ言われることもあります。
世間の流れだけではなく、社内の空気感や労働環境などへの要望、悩みなど、現場の声も変化している可能性があります。
そこに気づかずに一般的な流れで進めて失敗したというケースもあります。
教育方法の見直しが不十分
人材育成を行うために、計画を立てていると思います。
計画は定期的に見直しをしているでしょうか。
作った当時はどんなに良いものでも、時代が変われば教育カリキュラムも変えていかなくてはなりません。
以前は技術向上をメインとした研修等で良かったものが、現在ではメンタルヘルスや自己啓発に関するサポートも必要性を帯びています。
ITリテラシーに関する教育も必須と言えます。
誰しもがSNSのアカウントを持っている時代です。社員ひとりひとりにSNSの適切な運用方法を教育することは、会社を守るための重要なマネジメントのひとつと言えます。
時代にあった教育計画になっていなければ、効率的な育成は望めません。
人材育成の課題を解決する方法

ここまで人材育成を行う際に壁となる3つの課題をご紹介してきました。
その壁を超えるのは、簡単ではないかもしれませんが、絶対に無理でもありません。
越えるために、どのような考えや行動が必要なのか考えていきましょう。
時間管理の徹底
まずは時間の確保が必要です。
多くの企業ではOJT(現任訓練)と言われる、現場での実践を通して教育していく方法を採用しています。
良い人材を育てようと思うと、実務的な指導だけではなく、複数の社員全体に向けた集団研修も必要です。
そのためには、まとまった研修時間を確保する必要があります。
時間管理というと、スケジュール管理を想像するかもしれませんが、ここでいう時間管理は時間の確保を目的とするものです。
どの時間にどの研修を入れるかではなく、どのくらいの研修をしたいからその時間をどう捻出するかを考えるのが大切なのです。
時間を作るには、業務の見直しをし、効率良く仕事ができるように会社全体で改善策を講じる必要があります。
『時間は作るもの』と考えられるかどうかが、人材育成の重要なポイントです。
人材育成は管理職から
自社で人材育成を行おうとすると、担当する社員や管理職の教育から行うことが大切です。
人材育成には上司と部下、新入社員と先輩社員の人間関係も大切な要素です。
部下に対して、後輩に対してどのように接し、どのように指導をしていくのか、そのノウハウを身につけ実践し、リーダーシップを思う存分発揮してもらいましょう。
部署異動や新しいプロジェクトに参加させるなど、より多くの経験を積む機会を作っている企業は多いと思います。
その他にも、経営者を含めた管理職、教育担当者が集まり、育成に関する知識を共有をする場を設けるのも良いですね。
ジェネレーションギャップを埋める
人材育成には、指導する側とされる側の相互理解と信頼関係が必要です。
20代と50代では通ってきた道に違いがあり、学んできたことや指導されてきた内容は同じではありません。
自分の時代はこうだったから、今はこうだからというように、それぞれの視点からの考えや行動ではなく、お互いの考えや仕事の仕方について理解しあう姿勢を持つことが大切です。
「今の若いモンは・・・」
「昭和の考えは・・・」
と、言いたくなる気持ちもあるかもしれませんが、そこはグッと堪えて、お互いの話を聞き距離を縮めるところから始めてみましょう。
一方的に自分の主張したいことを言っても、課題解決にはなりません。
KeySessionでは貴社の管理職向け研修導入をお手伝いをいたします。
人材育成の課題を解決するポイント
人材育成は、企業の持続的成長に不可欠ですが、多くの企業でさまざまな課題が報告されています。これらの課題を解決するためのキーポイントを紹介します。
これらのポイントを押さえることで、人材育成の課題を効果的に解決し、企業の持続的成長を支える人材を育成することができます。
現状を把握し、課題を洗い出す
企業が直面している人材育成の現状を正確に把握し、具体的な課題を洗い出す必要があります。これには、現場の声を積極的に聞くことが重要です。スキルマップを作成して、必要なスキルや知識のギャップを明確にすることも有効です。
人材育成の目標を明確にする
明確な目標設定が、人材育成の成功には不可欠です。目標を設定する際には、「いつまでに」「どの程度まで」という具体的な数字を用いることが推奨されます。
必要な時間と予算を確保する
人材育成には、適切な時間と予算の確保が必要です。効率よく指導を進めるための工夫も求められます。
振り返りと軌道修正を行う
人材育成のプロセスには、PDCAサイクルを適用し、定期的な振り返りと必要に応じた軌道修正を行うことが大切です。特に、担当社員との面談やフィードバックの機会を設けることが推奨されます。
最適な育成手法を検討する
人材育成を効果的に進めるためには、自社の状況や目的に合った育成手法を選択することが重要です。例えば、忙しい部署の社員にはe-ラーニングのような柔軟な学習方法が適している場合があります。
階層別に人材育成を解説
新入社員/若手社員
新入社員や若手社員の人材育成では、学生から社会人へのマインドの切り替えが重要です。社会人としてのプロ意識を養い、ビジネススキルの基礎を身につけることが求められます。
具体的には、ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、そして基本的な業務知識などが挙げられます。この段階での育成には、新入社員研修や現場でのOJT(On-the-Job Training)が有効です。
OJTでは、先輩社員がメンターとなり、実務を通じて必要なスキルや知識を伝えることで、若手社員の早期戦力化を目指します。また、リアリティショックに対するサポートも重要であり、不安や疑問を解消するための個別面談や、内定者同士の交流の場を設けるなど、メンタルケアにも注力する必要があります。
若手社員が抱える可能性のある課題には、育成者の能力不足や、人材育成が計画的に行われていない点があります。これらの課題を解決するためには、育成計画の見直し、若手社員を育成するためのスキルアップ研修、そして加点方式での評価を導入することが効果的です。
KeySessionでは貴社のメンター研修導入をお手伝いをいたします。
中堅社員
中堅社員向けの人材育成では、彼らが直面する特有の課題に対応する必要があります。
中堅社員は一般的に、業務の基本スキルや知識を既に習得しており、日々の業務を遂行する上での問題は少ないです。しかし、キャリアの中盤に差し掛かると、彼らの成長やモチベーション維持、さらには管理職へのキャリアアップに向けた支援が求められます。
中堅社員の人材育成においては、目標管理や定期的な面談を通じた動機付け、キャリア形成を意識した教育、社外教育への費用負担、新しいスキルの習得支援など、彼らのニーズに合わせた取り組みが効果的です。具体的には、彼らの業務へのやる気を引き出すためには、彼ら自身のキャリアプランに基づく育成計画が必要です。また、組織や企業全体を見渡し、戦略的に仕事を遂行できるような視点や能力の向上も重要な焦点となります。
KeySessionでは貴社の中堅社員向け研修導入をお手伝いをいたします。
管理職
管理職の人材育成においては、階層別のアプローチが求められます。新任管理職には、プレイヤーから管理者へのマインドチェンジを促す教育が必要です。彼らには、個人の成果ではなく、チーム全体の成果を引き出す役割への理解を深めさせる研修が効果的です。
経験を積んだ中級・上級管理職に対しては、組織マネジメントや経営戦略、リーダーシップ、リスクマネジメントなど、より高度なスキルや応用力を高める教育が求められます。彼らには、自組織の課題を洗い出し、それに対する戦略を考え、実行に移せる能力の向上を目指すべきです。
管理職が抱える主な課題としては、部下の育成・指導力の不足、リーダーシップや実行力の強化が挙げられます。これらの課題に対応するためには、企業はマネジメントやコーチングの学習機会を提供し、人材育成の環境を整備する必要があります。特に管理職には、組織を率いるうえで欠かせない経営視点での判断力や、経営陣との連携能力の向上が求められるため、これらのスキルを磨く研修の提供が有効です。
管理職の人材育成では、その役割の理解を深め、組織や企業に対する貢献度を高めることが重要です。社外の研修を活用することも一つの方法であり、実務に応用できる実践的なスキルの習得を目指すべきです。
KeySessionでは貴社の管理職向け研修導入をお手伝いをいたします。
まとめ
人材育成を進める時に、『時間・意識・時代』が悩みの種になります。
3つの悩みを解消するには、時間管理の徹底、管理職の育成、ジェネレーションギャップを埋めることが重要です。
今ある宝(社員)を会社全体で磨き、将来のリーダー育てましょう!










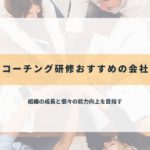


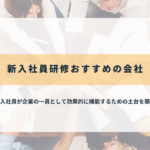


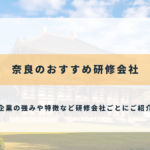

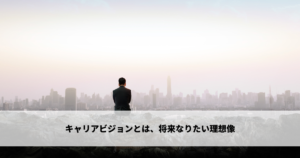
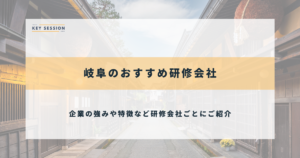
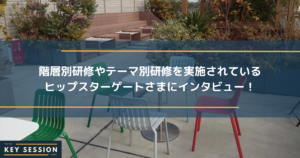
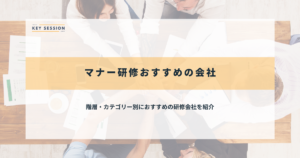
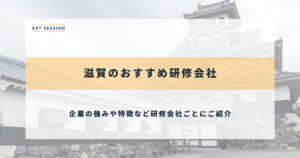

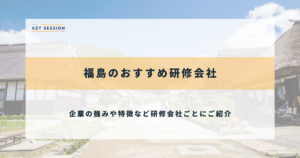
















 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート